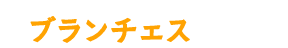10月26日(火)「トンボ」
トンボは、前にしか進まないことから、「不退転(ふたいてん)」の精神をあらわす「勝ち虫」として、戦国武将から縁起のいい物として愛されてきました。
古来、農耕民族であった日本人は、稲の益虫(えきちゅう)であるトンボを「田の神(たのかみ)」とあがめてきました。
弥生時代の銅鐸(どうたく)には、豊作を願ったと思われるトンボの図柄(ずがら)が描かれています。
トンボの古い呼び名「秋津(あきつ)」は、日本の国の古称(こしょう)でもあります。
日本の初代天皇である神武天皇が、国土を一望(いちぼう)して「秋津の雌雄(しゆう)が睦み(むつみ)合っているようだ」と形容したところから、日本を「秋津洲(あきつしま)」と呼ぶようになりました。
トンボは、最先端の航空工学からも注目されています。
4枚の薄い翅(はね)を前後別々に動かし、ホバリングから急旋回や宙返り、高速飛行など自由自在に飛ぶ能力を持っているからです。
その美しさから「水辺の宝石」とも呼ばれ、自然環境の豊かさを象徴するトンボは、私たちの身近にいるかけがえのない昆虫なのです。
一般社団法人倫理研究所 職場の教養10月26日(火)「トンボ」より
<今日の心がけ>
身近な生き物に目を向けましょう